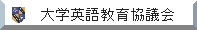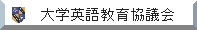
|
先に誤解のないよう言っておくと、これから書こうとすることは、別に英語学習の勧めとかそういうことではない。 2001年の2月、EU(欧州連合)の欧州委員会は、EU市民のうち自国語しか知らないという人は47%であるという調査結果を発表した。過半数(53%)の人は、自国語以外に何かしら外国語が出来るとのことだ。ルクセンブルクなど、自国語であるルクセンブルク語しか知らない人はわずか2%で、大概の人が三ヶ国語、人によっては四ヶ国語も使えるのだという。その他、スウェーデンやデンマークなど北欧諸国、またオランダ等でも、外国語に堪能な人の割合がひじょうに高いとか。 その一方で自国語しかわからないという人が多いのは、かつて植民地争奪に明け暮れ、今も世界各地に旧植民地を残すポルトガル、スペイン、フランス等。が、自国語しかわからない人が最も多いのは、やはり何と言ってもイギリスで、66%の人が英語以外は出来ないと答えたらしい。 この数字を多いと見るか少ないと見るか、人によって評価は分かれようが、イギリスにはかつて植民地だった国々から近年多くの移民が流入しており、その人たちは確実に英語の他にそれぞれの母国の言葉を話すことができるはずだから、これらの人たちの数を差し引いて考えれば、生粋のイギリス人で英語しか出来ない人の割合は66などという数字より、ぐんと跳ね上がることは間違いない。 なぜ多くのイギリス人は英語しか出来ないのか。なぜ外国語を身につけないのか。答は簡単。世界中どこへ行っても、相手側が英語を使ってくれるから、自分がわざわざ相手の言葉を学ぼうなんて気はさらさら起きないのだ。こうした事態を、当のイギリス人が、大変ありがたいこと、もしくは(自国の過去の植民地政策を思い起こして)申し訳ないこと…と考えているのならまだしもだが、どうもそうではないらしい。相手が英語を使うのは当然だ、俺たちはわざわざ外国語を学ぶ必要なんて無し!と信じ込んで疑わない、そういう手合いが少なくないようだ。  と言うのも、このEUの調査結果の真偽を確かめるべく、イギリスの新聞「ガーディアン」The Guardian の記者がロンドンのさまざまな場所へ敢えて英語以外の言語で電話を掛け、どういう反応が返ってくるか調べてみたところ、その結果は惨憺たるものであったらしいからだ。もちろん、中には欧州議会のロンドン事務所やマダム・タッソー蝋人形館のようにちゃんと外国語で受け答えしてくれたところもあったようだが、酷いのになると、例えば英国文化を海外に紹介することを目的としているはずの公的機関ブリティッシュ・カウンシルに雇用予定についてスペイン語で問合せてみたところ、"Inglais"(=スペイン語で「英語」の意)と連呼し(「英語で喋れよ、馬鹿野郎」ってことですか?)、最後には"Bye bye"と切られてしまったとか。また、バッキンガム宮殿に開いている時間帯をドイツ語で問合せてみたところ、"We speak English"と連呼(最後の方はいらいらしたように)するばかりだったとか。また、イギリスの有名なサッカーチーム「アースナル」の事務所にリヨンとの試合の切符の有無をフランス語で問合せてみたところ、"No tickets"(「お前なんかに売る切符はないよ」ということじゃないでしょうね?)と怒鳴るように連呼したとか。…いずれも「国際都市ロンドン」が聞いて呆れると言いたくなるような反応である。 と言うのも、このEUの調査結果の真偽を確かめるべく、イギリスの新聞「ガーディアン」The Guardian の記者がロンドンのさまざまな場所へ敢えて英語以外の言語で電話を掛け、どういう反応が返ってくるか調べてみたところ、その結果は惨憺たるものであったらしいからだ。もちろん、中には欧州議会のロンドン事務所やマダム・タッソー蝋人形館のようにちゃんと外国語で受け答えしてくれたところもあったようだが、酷いのになると、例えば英国文化を海外に紹介することを目的としているはずの公的機関ブリティッシュ・カウンシルに雇用予定についてスペイン語で問合せてみたところ、"Inglais"(=スペイン語で「英語」の意)と連呼し(「英語で喋れよ、馬鹿野郎」ってことですか?)、最後には"Bye bye"と切られてしまったとか。また、バッキンガム宮殿に開いている時間帯をドイツ語で問合せてみたところ、"We speak English"と連呼(最後の方はいらいらしたように)するばかりだったとか。また、イギリスの有名なサッカーチーム「アースナル」の事務所にリヨンとの試合の切符の有無をフランス語で問合せてみたところ、"No tickets"(「お前なんかに売る切符はないよ」ということじゃないでしょうね?)と怒鳴るように連呼したとか。…いずれも「国際都市ロンドン」が聞いて呆れると言いたくなるような反応である。日本人で日本語以外出来ないと言う人がどれだけの数字に上るかは知らないし(どの程度をもって「出来る」とするのかも問題だろうけど)、ひょっとしたらイギリスの66%よりずっと高いのかも知れないので、あまり偉そうなことは言えないのだが、それでも、外国語で電話が掛かってきた場合、上記のような態度に出る日本人は誰もいないのではないだろうか。 相手が英語を話すのが当然――、これはイギリス人にのみ見られる態度というのでなく、おそらくアメリカ人をはじめ英語を母国語とする人々の多く(もちろん決して全てではないが)についても事情は同じだろうと思われる。この一点からだけでも、「英語が話せたら国際人だ」とかいう言辞が如何にまやかしであるか、すぐにわかるというものだ。そういうまやかしを連日聞かされると、こんな横柄な人々を前にして、どうして我々の側だけがこんなに苦労して彼らの言語を学ばなければならないんだろうと、疑問が沸くのは極めて自然だと思われる。なぜ英語を学ばなければならないのか。それは「国際化」などという高尚そうなスローガンとは全く関係ない。ただただ、英語が世界各地で通用する可能性が一番高いらしいからという、利便性の問題でしかないのだ。 最後にちょっとイギリス人の弁護もしておきたいのだけれど、感心したのは、くだんの「ガーディアン」紙の記者たち、何と自社の「海外デスク」にも、そ知らぬ顔してスペイン語で電話を掛けてみているところ。そして、かなり惨憺たる、もしくは滑稽なる結果だったにも拘らず、それも堂々と記事にしているところだ。こういうイギリス人のユーモア精神は、英語以上に是非とも学びたいものだと思う。 I |
 関連ページ 「国際化」って何? へ
関連ページ 「国際化」って何? へ初稿 2002年